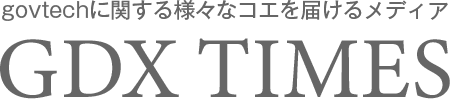index
市民自らがテクノロジーを活用して、生活上の悩みや課題を解決するのが「シビックテック(Civic Tech)」です。ここでは、発祥の地であるアメリカでどのように「シビックテック」の活動が活発化したかを振り返り、いよいよ根付きはじめた「日本におけるシビックテック」活動を紹介します。
シビックテック(CivicTech)とは

シビックテック(Civic Tech)とは何かについて紹介する前に、この言葉のもとになる「xTech(クロステック)」について見ていきます。
「シビックテック(CivicTech)」という言葉を生んだ「xTech(クロステック)」
デジタル技術の進化、発展によって、人々の暮らしや働き方は大きく変化しています。AIやIoT、ビッグデータ分析などの先端技術の導入によって、新たなサービスの創出やビジネスモデルの変革が進んでいます。このような変化が進むなかで、「xTech(クロステック)」という言葉を耳にするようになりました。掛け合わせるという意味の「x」と「Tech(=Technology)」をつないで、「既存産業と先端技術を掛け合わせることでイノベーションを起こしていく動き」を表しています。
たとえば、Finance(金融)とTechnologyを掛け合わせた「FinTech」は、ICTの活用によって金融業界にもたらされた新たな進化を意味します。オンラインバンキングやキャッシュレス決済の実現、仮想通貨やクラウドファンディングなどもFinTechを活用したサービスです。「Government(政府)」と「Technology(技術)」を掛け合わせた「GovTech(ガブテック)」もまた「xTech」のひとつで、国や地方自治体が提供する行政サービスに最先端のデジタル技術を活用しようという取り組みです。
このほか、教育や医療、農業、不動産、スポーツなど、幅広い業界や業種、分野で「xTech」の動きが見られます。
「シビックテック(CivicTech)」は「市民×テクノロジー」
市民(Civic)が自らの生活課題の解決に向けてテクノロジーの活用を図ろうとする動きを、「シビックテック(CivicTech)と呼んでいます。
少子高齢化や地域間格差の拡大など、現代社会が抱えるさまざまな社会課題の解決を図るために、政府は「未来社会のあるべき姿」を提唱し、IoTやAIなど最先端のテクノロジーを用いた施策を打ち出して、段階的に実施してきました。しかしながら、これらは政府主導の施策であって、それぞれの市民が目の前に抱える課題にヒットし、それらを解決へと導くものには必ずしもなり得ていないというのが現状です。
「シビックテック(CivicTech)」は、市民自らがテクノロジーを活用して、政府が打ち出す施策だけでは解決できない「今日を生きるために不可欠な悩みや課題」の解消に取り組む動きをさしています。ICTに関する知識や技術を備えた市民自らが主体となって、シビックテックの取り組みを支えています。
シビックテック(CivicTech)はアメリカが発祥
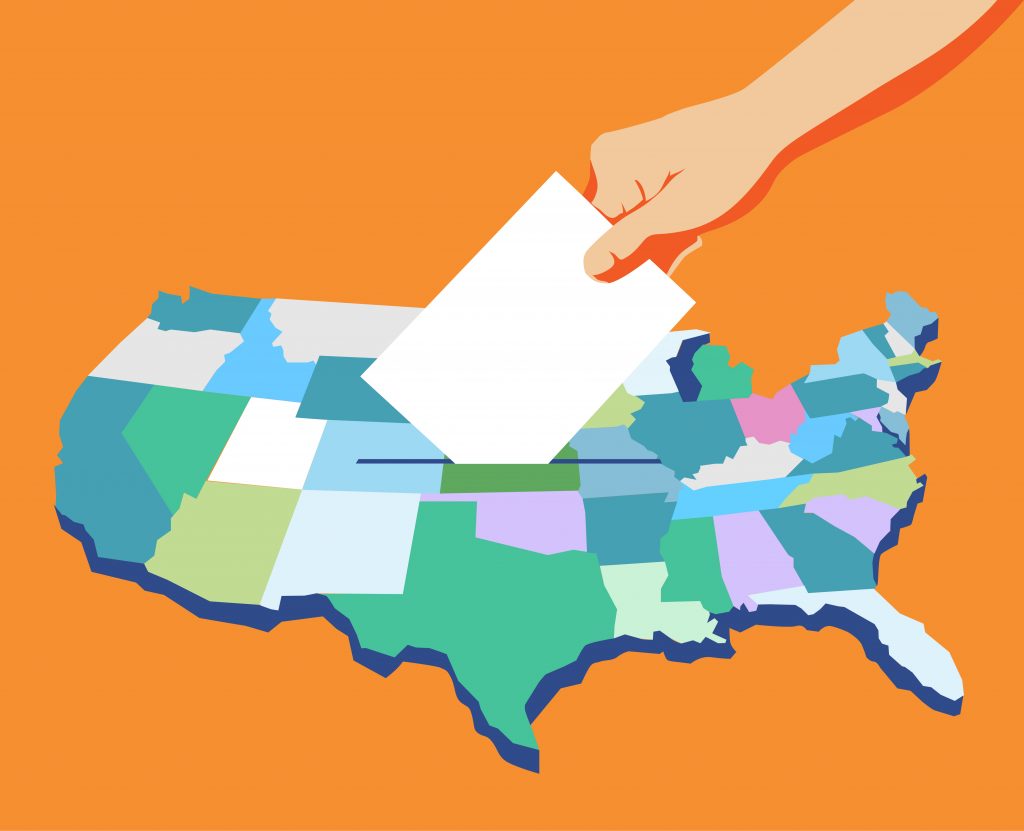
「シビックテック(CivicTech)」発祥の地とされるアメリカにおいて、どのような動きがあったのかを見ていきましょう。先行しているアメリカの歴史をたどることによって、今後の動き方のヒントが見えてきます。
2009年「ガバメント2.0」が契機
米国政府は、長期にわたり多くの予算をかけて行政サービスを構築して市民に提供してきましたが、2000年代に入ると、多様化する市民のすべての要望をかなえるサービス提供が困難となり、新たなテクノロジーへの対応にも支障をきたすことが多くなっていきました。
こうしたなか、オライリーメディア社の創始者であるティム・オライリー氏は「そもそも社会を築くのは市民である」として、利用者視点に基づく行政サービスの構築を専門家や市民に任せて、政府や地方自治体は行政サービスの提供に関わるルールづくりや円滑な運用を実現するための場(プラットフォーム)づくりに専念すべきという「ガバメント2.0」の概念を提唱しました。
「ガバメント2.0」は、市民社会に新たな挑戦の場を提供するものであり、多くの社会課題に向き合い、それらを解決に導くために、新たなサービスやビジネスモデルを創出可能な社会を築き上げることを目的としています。
この「ガバメント2.0」の提唱を機に、国や自治体が保有しているデータは、利用者である市民が自由に加工、分析できるかたちで公開されるようになり、市民参加型のオープンガバメントへと発展していく契機となりました。そして、市民自らがテクノロジーを活用して、それまで使いづらさを感じてきた行政サービスを改善していくシビックテックの取り組みがスタートすることになりました。
米国シビックテックを代表するCode for America
米国におけるシビックテックの先駆けとなり、現在では世界のシビックテックを代表する存在となったのが、2009年に発足した非営利組織「Code for America」です。
「Code for America」のアプローチは、米国政府や自治体に、全米から募ったITエンジニアを「1年間限定の派遣」で提供するというものです。行政府などに送り込まれるエンジニアたちを「フェロー」と呼びますが、彼らはそれぞれの派遣先の課題や問題点を担当スタッフにヒアリングし、ウェブサイトの改善やアプリの開発に従事します。イベントを開催して市民の声を集め、ウェブサイトの構築に反映することもあります。
各行政府が抱える課題を解決するためのプロジェクトへの参加を希望するエンジニアの数は年を追うごとに増加しているといいます。「Code for America」は、民間のスキルを行政の問題解決に役立てるプラットフォームとして絶大な支持を得ています。
日本でのシビックテック活動

日本国内でのシビックテックは、2013年5月、石川県金沢市に「Code for Kanazawa」が立ち上がったのを皮切りに、各地でさまざまな活動が展開されるようになりました。その多くは市民が抱える悩みや課題に寄り添い、その解決を支えていくという草の根的な取り組みでした。
これに対して、米国のような行政府とシビックテックの連携で注目されたのが、2011年3月11日の東日本大震災後の対応です。民間企業が安否確認のためのサイトを立ち上げ、全国の個人エンジニアたちが救援物資や交通情報、電力使用量など震災関連の情報提供サイトを構築するなど、市民主導で行政を支援しようとしたのです。
2013年にシビックテック団体「Code for Japan」を設立し、代表理事を務める関 治之氏は、2011年の東日本大震災が発生した4時間後に、オープンソースのソフトウエアを活用した復興支援プラットフォーム「sinsai.info」を開設。SNSを通じて得られた情報を加工して、迅速な情報発信を行いました。
コロナ禍で誕生したシビックテック活動

活動事例1|東京都 新型コロナウイルス感染症対策サイト
東京都からの依頼を受けて構築された「新型コロナウイルス感染症対策サイト」は、2020年3月に開設されました。東京都におけるコロナウイルスの感染者数、検査数などをグラフなどでわかりやすく表現。外部の人や企業が分析に使えるように、データはオープンデータとして公開しています。
活動事例2|VS COVID19アイディアボックス
コロナウイルス対策におけるアイデアを広く集めるために立ち上げたのが「VS COVID19アイディアボックス」です。一方通行の掲示板ではなく、寄せられた意見に対して、経産省や総務省、内閣官房の事務局などからの回答や返事が、即日で返されるのが特長です。すぐに反応があるために、数多くのアイデアが寄せられるという好循環が生まれました。2020年5月13日から6月5日までの期間限定で運営されましたが、現在は閲覧できません。
市民が主体となって、自らが抱える課題を解決するために、テクノロジーを活用するのが「シビックテック」です。すべてを国や行政府任せにするのではなく、市民自らが問題意識を持って、自分たちが欲する未来を、自分たちの知恵やアイデアで築いていくところに「シビックテック」の価値があるのではないでしょうか。