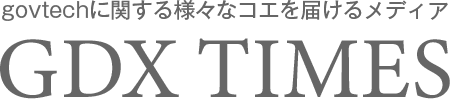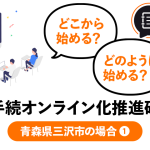- HOME
- AUKOE の コエ
- 保育の「つまずき」はどこで生まれるのか
保育の「つまずき」はどこで生まれるのか
- category : AUKOE の コエ etc
 #Pickup記事
#子育て
#手続・申請
#Pickup記事
#子育て
#手続・申請
- writer : GDX TIMES編集部
index
少子化対策の柱として子育て支援制度の拡充が進むなか、現場では「情報は公開されていても行動につながらない」という課題に各自治体が対策を講じ始めています。情報発信・デジタル化といった視点と、利用者視点の観点から、自治体DXが取り組むべき方向性を探ります。
保育DXの推進
少子化が加速するなかで、子育て支援分野では制度拡充や対象範囲の拡大が相次ぎました。保育分野においては、これまでの政策に加え「こども誰でも通園制度」や「保育所等における医療的ケア児への支援」なども拡充され、利用者が多様な保育サービスを受けられる状況になっています。
また、保育施設のIT導入により業務負荷を軽減し保育の質の確保の動きは顕著で、令和7年度中に保育ICT導入率100%を目指すという政府方針は変わらず保持されています。
一方、自治体の保育現場としては、自治体窓口DXの推進が進むなか、保育特有の課題に対応する必要があり、単なる電子化・オンライン化では利用者が利便性を感じられず、結果として自治体のDXも進まないという状況が発生します。
保育給付や関連助成制度の対象世帯拡大は、多くの家庭にとって朗報である一方、自治体には利用者にしっかり届く情報発信と、利用者が理解できる申請の案内を行うことは、職員の業務負担を減らすうえでもますます重要になっています。政策の追い風が現場の業務負担増加とならない工夫が必要です。
どこでつまずくのか? 情報はあっても「行動」につながらない7つの要因
自治体サイトや入園案内に情報は掲載されていても、自力で申請完了するまでには多大な時間がかかること、また時間をかけて申請しても書類不備や理解不足があり申請完了できないケースなどが後を絶ちません。背景には、以下のとおり、住民の行動・情報取得 プロセスと情報提供の設計が噛み合っていないという構造的な要因があります。
- 情報の並びが“制度起点”で、住民の“状況起点”とズレる
制度ごとに説明が分かれているため、「自分は対象か/何を準備すべきか」を最初に確かめたい住民の行動と噛み合わない。
- 分岐と例外が多く、自己判定が難しい
認定区分(就労・求職・疾病・介護・在学など)や世帯事情で必要書類が大きく変わる。注記・但し書きが多く、読み解きに負荷がかかる。
- 用語・様式のハードル
「認定区分」「保育必要量」「就労証明」等の専門語、PDF中心の説明、スマホで読みにくい文書が理解を妨げる。
- “役所外”で取得する書類がボトルネック
就労証明(勤務先)、診断書(医療機関)、母子健康手帳の写し等、第三者を巻き込む準備が必要。リードタイムの見通しが立たず、漏れや差し戻しが起きやすい。
- 導線の分断(情報→申請の切れ目)
案内ページと電子申請・ダウンロードが別システム/別ページで分かれ、途中で要件(電子署名、アカウント作成等)が突然現れて離脱を招く。
- 更新が多く、案内がバラバラ
制度のルールや提出書類は頻繁に変わるため、ホームページのページごとに説明が食い違うことも。窓口担当者の説明の仕方によって 異なるように受け取られることもあり、住民の混乱を招きやすい。
- 繁忙期に業務が集中することで対応が追いつかない
募集時期や年度替わりは、問い合わせや手続きが一気に増える「繁忙期」。自治体も説明会や案内を工夫しているものの、業務量そのものが急増するため、住民へのフォローが行き届かず、不備や滞留が起きやすい。
「公平性・利用しやすさ・効率化」を保育分野でどう対応するか
こうした現場課題を受け、こども家庭庁の各種資料では繰り返しこの3点が重視されています。
公平性|情報格差を制度格差にしない
保育制度は条件や書類が複雑で、「自分が対象か」「何を準備すべきか」が理解できないために利用の機会損失が生まれている可能性があります。もっとも支援を必要とする家庭ほど取り残されるリスクがあるため、「誰にでも公平に届いているか」が政策の有効性を測る最優先の軸になります。
利用しやすさ|誰でも迷わずたどり着ける設計にする
情報が公開されていても、専門用語が多かったり、PDF前提でスマホから読みにくかったりすると、利用に至らない住民が出てしまいます。形式や設計が障壁になれば特定の層が排除されることになり、制度の趣旨が損なわれます。
なお国は、ウェブ分野において「アクセシビリティ(JIS X 8341-3準拠)」を求めています。これは高齢者や障がいのある方を含め、誰もが情報にアクセスできるようにする取り組みです。本稿ではアクセシビリティの担保はもちろん、より広い意味で「制度の利用しやすさ」は情報提供のあり方、申請のしやすさも含めたユーザーエクスペリエンスの課題として解釈しています。
効率化|続けられる仕組みをつくる
制度が拡充する一方で、自治体の人員や予算は限られています。窓口対応や書類確認に追われれば、本来の住民支援に割く時間が減ってしまいます。効率化は単なる省力化ではなく、制度を持続的に運用し続けるための条件です。オンライン予約・申請、ワンスオンリー化はその典型で、住民・職員双方の負担を減らす狙いがあります。
また、こども家庭庁からは、「こども政策DXモデル事業 事例集(概要版)」も公開され、以下の団体の事例が掲載されています。
- 岩手県一関市
- 東京都青梅市
- 東京都東村山市
- 東京都府中市
- 新潟県糸魚川市
- 大阪府和泉市
- 沖縄県沖縄市
- 沖縄県那覇市・南城市・西原町
政策の追い風を「住民体験」へつなぐ
子育て支援制度は今後も拡充を続けます。制度が広がるほど、住民は「自分に関係あるのか」「何を準備すればいいのか」で迷いやすくなります。
だからこそ自治体に求められるのは、迷いを先回りして取り除く仕組みを整えること。国の方針と政策の流れを住民体験に落とし込み、制度を公平に、わかりやすく、効率的に届けることが、これからの子育て支援DXの本質です。